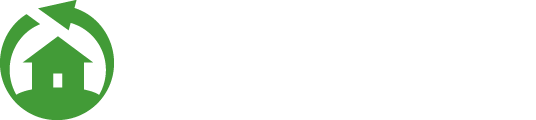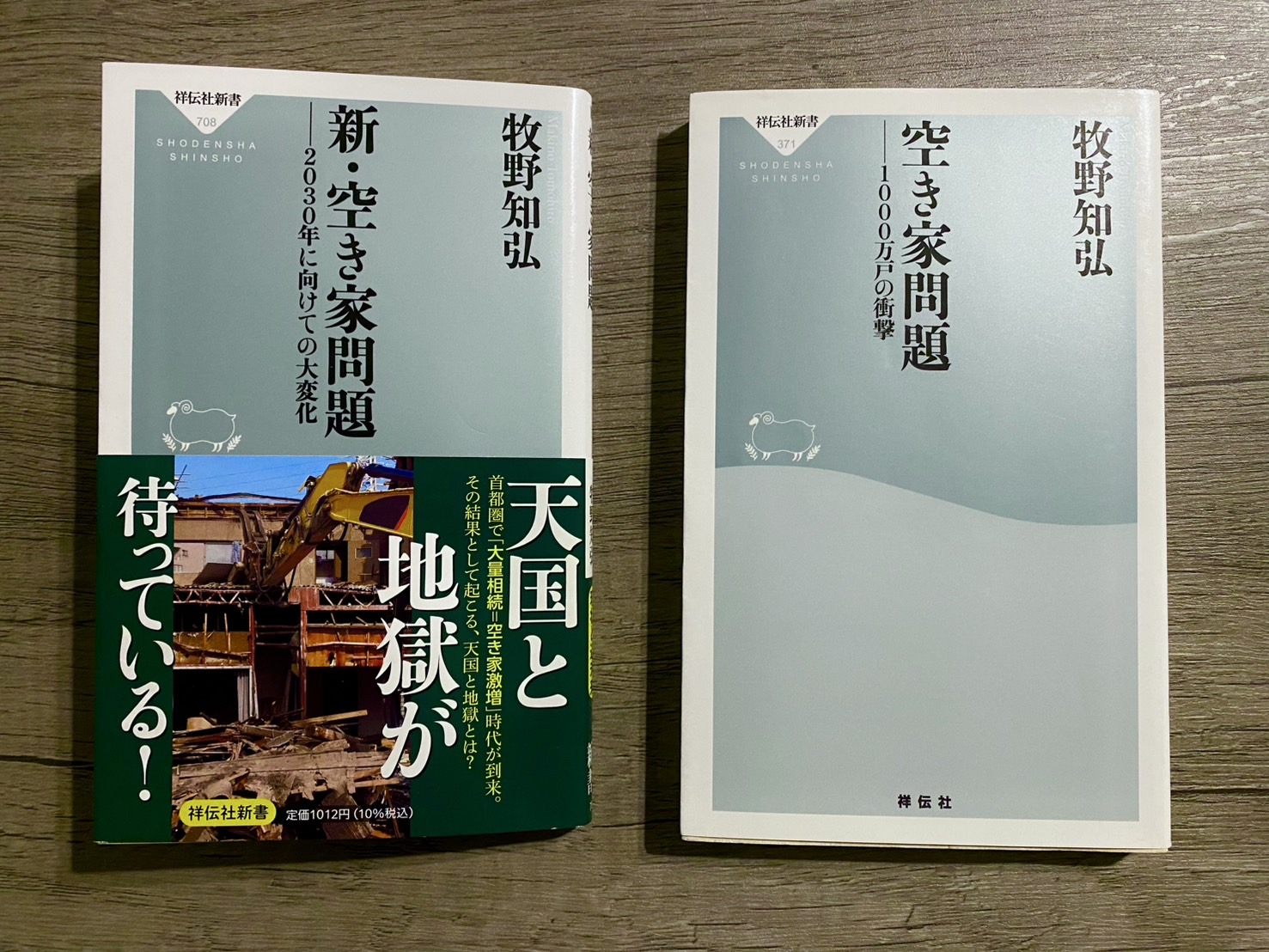
2014年に刊行された『空き家問題』は当時ベストセラーとなり、空き家の増加が社会問題として認識され始める契機となりました。しかし、当時は主に地方の問題として捉えられていたものの、それから10年が経過した現在では、大都市圏の郊外にも広がり、全国的な課題となっています。
2025年2月に発刊された『新・空き家問題』では、この10年間での状況の変化に焦点を当て、現状分析だけでなく、具体的な対策や今後の展望についても詳しく解説されています。本書は不動産業界関係者だけでなく、一般の方々にとっても非常に参考になる内容となっています。
空き家の現状と今後の見通し
2024年4月に総務省が発表した住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家は900万1600戸に達し、住宅総数の13.8%を占めています。これは、日本の住宅7軒に1軒が空き家であることを意味し、2018年の前回調査と比較して51万戸(6.0%)の増加が確認されています。
空き家は「賃貸用」「売却用」「二次的利用(別荘など)」「その他(放置された個人住宅)」の4つに分類されます。この中で最も多いのは賃貸用空き家で、全体の49.3%を占めています。特に築年数の古い物件が市場競争に敗れ、空き家化している状況が明らかになっています。
また、個人所有の空き家は385万6000戸に上り、2018年の調査から10.6%増加しました。これは相続や税制対策の影響が背景にあります。多くの相続人が固定資産税や管理の負担を避けるため、売却や賃貸の選択をせず、結果として放置されるケースが増えているのです。
増加するマンション空き家の問題
空き家の半数以上はマンションの空き住戸!
空き家と聞くと、多くの人は戸建て住宅を思い浮かべるでしょう。メディアに取り上げられる、誰も住まなくなった家やゴミ屋敷化した物件は、視覚的なインパクトが強く、話題になりやすいからです。また、空き家は周辺環境の悪化や治安の低下、さらには災害時の避難路の妨げなど、多くの問題を引き起こす要因とされています。
しかし、近年急速に増えているのは、マンションなどの共同住宅における空き住戸です。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、日本全国の空き家のうち、共同住宅の空き住戸は502万9000戸にも及び、これは全空き家の56.1%を占めています。
マンションは戸建てとは異なり、一目で空き住戸かどうかを判断しにくいのが特徴です。郵便受けにチラシや郵便物が溜まる、管理費や修繕積立金の滞納が発生するといった間接的なサインがあるものの、外部からは気づきにくいのが実情です。
マンション空き住戸が引き起こす問題
一般的に、鉄筋コンクリート造のマンションは耐久性が高く、建物の劣化が遅いと考えられています。しかし、空き住戸の増加によって以下のような問題が発生します。
1. 配管メンテナンスの支障
マンションの排水管は定期的にバキューム清掃を行うことで詰まりを防ぎます。しかし、空き住戸の所有者が対応しないと、その住戸の清掃ができず、マンション全体の排水環境が悪化します。
2. 消防設備の点検不備
火災報知器や消火設備の点検ができないと、火災発生時に被害が拡大するリスクがあります。
3. 水漏れ・害獣問題
長期間放置された住戸では、水道設備の劣化による水漏れが階下へ影響を及ぼしたり、ベランダにハトが巣を作るなど、衛生環境が悪化するケースもあります。
4. 修繕積立金の不足
空き住戸が増えると、管理費や修繕積立金の滞納が発生し、必要な修繕ができなくなります。結果として、マンション全体の資産価値が低下します。
このように、マンションは戸建てよりも所有者個人での対策が難しく、空き住戸が増えることでより深刻な問題を引き起こします。
なぜ空き住戸が増えるのか
国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、2022年末時点で築40年以上のマンションは125万7000戸あり、10年後の2032年には260万8000戸、2042年には445万戸に増加すると予測されています。
築40年以上のマンションでは、購入当初30代〜40代だった所有者が70代〜80代に達し、子供の独立、夫婦のどちらかが他界、高齢者施設への入居などにより、単身世帯が増加。最終的に相続が発生し、空き住戸化が進んでいきます。
また、相続されたマンションが放置される背景には、以下のような要因があります。
* 戸建てと異なり、外部から管理状況が分かりにくい
* 管理人が共用部を清掃するため、放置しても目立たない
* オートロックがあるため、防犯上の問題意識が低い
* 郵便受けにテープを貼るだけで郵便物の蓄積を防げる
これらの理由から、相続人は空き住戸をあまり問題と捉えず、積極的に管理しようとせず、結果として放置されてしまうのです。
管理不全マンションの実態
管理が不十分なマンションは、資産価値が下がり、売却や賃貸が難しくなります。また、住人の高齢化に伴い、住戸内での孤独死が増加。内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によれば、東京23区内で65歳以上の一人暮らしの自宅死亡者数は2022年に4868人に達し、2012年の2733人から1.78倍に増加しています。こうした孤独死の後、相続人が物件を管理せず、空き住戸が放置されるケースも少なくありません。
外国人所有のマンションが空き住戸化する背景
最近では、都心の高級マンションを外国人が購入するケースが増えています。特に中国、韓国、台湾、香港などの東アジア圏の富裕層が、日本の物価の安さに魅力を感じ、投資目的で購入する傾向があります。
しかし、こうした外国人オーナーの多くは、日本を訪れる際の「宿泊施設」としてマンションを購入しており、利用頻度が低下すると放置されるケースが目立ちます。この現象は、所有者が頻繁に訪れる初期段階では問題になりませんが、時間の経過とともに管理が行き届かなくなり、結果的に空き住戸化していくのです。
流動化できない築古・郊外マンションの行く末
以前はマンションは流動性が高く、戸建てよりも売却しやすいとされていました。しかし、築年数が古くなると、管理状態の悪化、修繕積立金の不足、立地の問題(郊外や駅遠の物件) が影響し、売却が難しくなります。結果として、築古・郊外のマンションは市場で動かなくなり、空き住戸のまま放置されるケースが増加しています。
マンションの空き住戸問題は、戸建ての空き家以上に複雑で深刻です。管理費の滞納、修繕の遅れ、防災面でのリスクなど、多くの問題を内包しており、今後さらに拡大する可能性があります。空き住戸の増加を防ぐためには、適切な管理体制の確立や、所有者意識の向上が不可欠です。
まとめ
『新・空き家問題』では、空き家問題が地方にとどまらず、大都市圏にも広がっている現状を詳細に分析しています。特にマンションの空き住戸問題や、相続がもたらす影響についての指摘は、今後の不動産市場を考える上で非常に重要です。
私たち一人ひとりが空き家問題を「他人事」ではなく「自分ごと」として捉え、適切な対応を行うことが求められています。本書を通じて、これからの日本社会の課題についてより深く考察して行くことができるはずです。気になった方はぜひ書籍を読んでみてください。
新・空き家問題ーー2030年に向けての大変化
祥伝社新書
牧野 知弘 (著)
(以下、目次より)
●空き家900万戸の衝撃
●空き家の半分以上はマンション空き住戸
●実は世田谷区は空き家天国だった
●おひとりさま老後のリアル
●ついに、国が重い腰を上げた
●絶対に押さえておきたい法改正
●親の財産を知ることから、空き家対策が始まる
●相続登記をしないと……
●空き家バンクを活用しよう
●不動産投資ブームに群がる人たち
●2030年以降に起こる大変化
●都内優良住宅が大量にマーケットに
●住宅量産政策からの転換
●街プラウドの醸成が空き家をなくす
AMAZON:ストアリンク