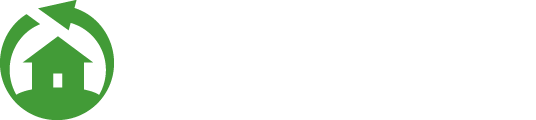実家のおうちじまい
昨今、メディアでよく取り上げられている日本の空き家問題。それにともない「実家じまい」という言葉をよく耳にするようになりました。
「おうちじまい」は単に家の処分を指すのに対し、「実家じまい」とは、親が住まなくなった実家を売却・処分することを指します。
近年、日本では核家族化が進み、親と子供が別々に暮らすことが一般的になっています。そのため、親が住まなくなった家が空き家となるケースが増えています。空き家は誰も住まなくなると老朽化が進み、適切な維持管理が必要となります。
しかし、現代の多忙なライフスタイルの中で、その子供たちが空き家を管理するのは容易ではありません。
また、空き家の状態によっては近隣住民に迷惑をかけることもあり、その負担を軽減するために実家じまいを検討する人が増えています。
実家のおうちじまいを考えるタイミング
実家じまいを検討するタイミングとして、以下の状況が挙げられます。
1. 相続が発生して実家が空き家になった場合
2. 親が施設に入居し、実家が空き家になった場合
3. 空き家の維持管理が負担になった場合
▽相続が発生して実家が空き家になった場合
親の相続が発生し、実家が空き家になった場合、実家を売却して得た資金を相続人で分配する「換価分割」を行うことが一般的です。換価分割を行う際には、法律や税金の問題が関わるため、複雑なケースの場合は専門知識を持つ税理士に相談することをおすすめします。相続登記や税務手続きなど期限が決まっているため、相続が決まった場合は早めに手続きを行うことが重要です。
▽親が施設に入居し、実家が空き家になった場合
親が高齢者施設に入居し、実家が空き家になる場合、施設の入居費用を捻出するために実家を売却するケースも多く見られます。誰も住まない家を維持するより、速やかに売却し、施設費用に充てることは合理的な判断と言えます。
しかし、親が長年住んでいた家には多くの思い出が詰まっており、簡単には手放せないと感じる方も多いです。実家じまいは親の同意が必要なため、丁寧に時間をかけて説明し、納得してもらうことが大切です。
▽空き家の維持管理が負担になった場合
空き家の維持管理が負担となり、実家じまいを決断する方も増えています。管理が行き届かないと、老朽化が進むだけでなく、近隣に迷惑をかける可能性もあります。
特に地方にある実家の場合、処分が困難なこともあるため、自治体の「空き家バンク」を活用するなどの選択肢がありますが、一部の市町村では、空き家バンクの制度が殆ど機能していない、もしくは廃止になったというケースも見受けられます。
単に手続きが面倒で放置していたり、気持ちの整理がつかず空き家を残しているという場合が多いので、専門知識を持った民間事業者が主体となり、空き家の対処をサポートすることが求められます。

実家のおうちじまいは親が亡くなる前と後、どちらが最適?
「実家じまいは親が亡くなる前と後、どちらのタイミングが良いですか?」という質問をよくいただきます。しかし、最適なタイミングはそれぞれの状況によって異なり、一概には言えません。
親の死後には相続が関係するため、法律や税金の観点から慎重に判断する必要があります。
■親が存命中に実家じまいをするメリット・デメリット
親が生きているうちに実家を処分する最大のメリットは、売却した資金を老後の生活費や介護施設の入居費用に充てられる点です。また、不動産は遺産分割の際にトラブルになりやすいため、事前に現金化しておくことで、相続時の家族間の争いを防ぐことができます。
一方、デメリットとしては、不動産を現金化することで資産評価額が上がり、結果として相続税が増えてしまう可能性がある点です。また、親が「やっぱり家に戻りたい」と希望した場合、すでに処分してしまったため対応できないといった問題も考えられます。
■親の死後に実家じまいをするメリット・デメリット
親が亡くなった後に実家を処分することで、相続税の評価額を抑えられるほか、「空き家の3,000万円特別控除」を活用できるといった税務上のメリットがあります。
また、生前に親が認知症だった場合、成年後見人を立てないと売却できませんが、相続後であれば子どもたちの意思で売却し、資産を分けることが可能です。
しかし、デメリットとしては、相続手続きと並行して実家の処分を進める必要があるため、手続きが複雑化する点が挙げられます。スムーズに進めるためには、司法書士や税理士、相続に関する専門家に相談することをおすすめします。

実家じまいで直面しやすい課題
実家じまいを進める際には、次のような課題があります。特に多くの方が直面している問題としては家族間での話し合いの難しさや、立地条件の都合で売れづらいなどの課題があります。
▽親を説得するのが難しい
実家の所有者は親であり、子どもたちではありません。不動産の売却には所有者の同意が不可欠なため、まず親に「実家じまい(売却)」について理解してもらう必要があります。
多くの家庭で、子どもたちが売却を望んでいても、親は思い出の詰まった家を手放したくないと考えがちです。そのため、親の気持ちを尊重しつつ、将来的な負担について丁寧に話し合うことが大切です。「親が元気なうちは実家を残しておこう」と考えるケースも多いですが、早めの検討がスムーズな実家じまいの鍵となります。
▽親が認知症になってしまった
不動産売却は法律に定められた行為のため、所有者には売却を判断できる「意思能力」が必要です。しかし、親が認知症を発症して意思能力を失ってしまうと、家を売ることができなくなります。この状態になると、子どもたちがどれほど売却を望んでも実行は難しく、実家の売却は困難となります。解決策として、成年後見人を選任することで、法的手続きを進めることも可能ですが、認知症の進行具合の段階によって後見人として認められるための様々な基準をクリアしないといけないため、早い段階で親の意思や今後の方針について確認しておくことが重要です。
▽田舎の家は売れづらい
地方や過疎地域では、人口減少が進み、空き家が増加しているため、実家を売却するのが困難なケースが多々あります。このような場合、近隣住民への相談や自治体の空き家バンクの活用や、民間の事業者が提供している空き家マッチングサービスを利用したり、売却だけでなく賃貸物件としての活用を検討するなど、複数の選択肢が考えられます。地方の不動産市場は今後さらに厳しくなることが予想されるため、売主としては価格を柔軟に見直す姿勢も必要かもしれません。
▽家族間で意見がまとまらない
実家じまいを進めるうえで、家族の意見が一致しないことも大きな課題となります。親は「できるだけ住み続けたい」と考える一方で、子どもたちは「早めに売却したい」と意見が分かれることがよくあります。さらに、兄弟姉妹の間でも、実家を残すべきか、売却すべきか、あるいは相続の方法について異なる考えを持つことがあり、話し合いが難航するケースも少なくありません。
家族間で意見が対立すると、実家じまいがなかなか進まず、維持費や管理の負担が増える一方となることも。こうした事態を避けるためにも、早い段階から家族全員でじっくりと話し合い、将来のビジョンを共有することが大切です。第三者として専門家(終活カウンセラーや相続診断士など)を交えて意見を調整するのも有効な方法です。

建物を解体することで
実家じまいを進める際、空き家となった建物を解体すべきかどうかを検討する必要があります。
「近隣に迷惑をかけるかもしれないから解体したほうがいいのでは?」と考える方も多いでしょう。しかし、少しお待ちください。場合によっては、空き家を解体せずに残しておいたほうがメリットがあることも覚えておきましょう。
■空き家を解体すると固定資産税が増加する?
土地や建物を所有していると、「固定資産税」が課せられます。住宅として使用されている土地は、住宅用地の特例により税額が軽減されます。 しかし、建物を解体してしまうとこの特例が適用されなくなり、翌年から固定資産税が大幅に増額されることになります。
■売却時の税務特例が適用できなくなる?
不動産を売却する際には「譲渡所得税」が発生する可能性があります。この税金は売却益に対して約20%(短期譲渡の場合は約40%)と高額になるため、特に注意が必要です。
家の売却の際の譲渡益から3,000万円を控除できる「マイホーム特例」や「空き家の特例」がありますが、これらの特例は建物が存在していることが条件となるため、解体してしまうと適用できなくなります。近隣の目を気にして早急に解体を考える方もいらっしゃいますが、まずは専門家に相談することをおすすめします。
■田舎では建物があるほうが売却しやすい?
都市部(東京都内や大阪など)では、土地の価値が高いため、更地にしても問題なく売却が可能です。しかし、地方や田舎では土地の価値が低く、建物があったほうが売却しやすい傾向にあります。
地方では、古い家屋でも買い手が見つかることが多いため、解体せずに残しておくことが有利な場合があります。ただし、空き家付きで売却する場合、建物の欠陥に対する修理義務(契約不適合責任)が発生したり、税務特例が適用できなかったりするなど、別の問題も生じます。
都市部と地方では最適な売却方法が異なりますので、専門家と相談しながら慎重に進めることが重要です。
実家じまいにかかる費用
実家じまいにはさまざまな費用(経費)がかかります。ここでは司法書士や不動産会社に依頼して家じまいを行った場合に発生する費用をあげてみました。
[経費]
■不動産会社へ支払う仲介手数料
売却価格の3%+6万円(税別)
実家を売却する際に、不動産会社に支払う手数料です。物件の広告や購入希望者の紹介、契約手続きなどのサポートに対する対価となります。通常、売却価格の数%がかかります。
■測量費用、境界確定費用
小規模な土地(100坪以下)の場合、10万〜50万円
土地の正確な広さや境界線を確認するために専門家(測量士など)が行う作業にかかる費用です。土地の売却時に、隣地とのトラブルを防ぐために重要です。
■家の中の残置物撤去費用
30万~100万円(家財の量による)
実家に残っている家具や家電、生活用品などを処分するための費用です。自治体の処分サービスや専門業者に依頼することができます。
■建物解体費用
売却前の更地化など:100万~300万円
家を取り壊して更地にするためにかかる費用です。土地の売却条件によっては、買主が更地を希望する場合があり、その場合に必要になります。
■建物滅失登記代、土地家屋調査士報酬
5万円~10万円
建物を解体した後、登記簿上から建物の存在を抹消するための手続き費用です。土地家屋調査士が申請を代行することが多く、その場合報酬が必要です。
■相続登記代、司法書士報酬
10万~50万円
実家を相続した場合、その名義を相続人へ変更する手続きにかかる費用です。司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
■その他、交通費等の実費
実家の整理や手続きのために現地へ行く際の交通費や、書類取得などにかかる細かい費用です。
[税金]
■譲渡所得税
家を売却して利益が出た場合にかかる税金です。税率は売却した年数などによって異なります。
マイホーム控除(3,000万円控除)をうまく活用すれば税金を大幅に軽減可能。
■相続登記の登録免許税
固定資産評価額×0.4%
相続登記を行う際に、不動産の評価額に基づいて支払う税金です。不動産の名義変更の際に必ず発生します。
■売買契約書に貼付する収入印紙
不動産売買契約を結ぶ際、契約書に貼ることで課税される税金です。売却金額によって必要な印紙の額が変わります。
このように実家じまいには色々な費用が発生します。特に建物解体費用は数百万円単位になることもあるため、事前に必要な費用をしっかりと把握し、計画を立てることが大切です。
まとめ
実家のおうちじまいは、親や家族の思いを尊重しながらも、現実的な課題に向き合う必要がある重要な決断です。相続や税金、売却の手続きなど専門知識が求められる場面も多く、早めの計画と家族全員での話し合いが鍵となります。また、実家の状態や地域によって最適な方法が異なるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
空き家再生協会では、空き家問題に取り組む専門家を育成する「空き家再生士」の資格取得をサポートしています。おうちじまいを含め、空き家の有効活用をお考えの方は、ぜひ資格案内ページをご覧ください。
空き家再生士資格の案内はこちら
専門的な知識とスキルを活かして、空き家問題の解決に一歩踏み出してみませんか?