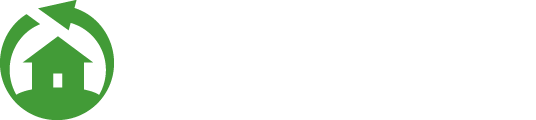先日、慶應義塾大学商学部で経営学の教授・横田絵里先生のもとで研究している劉さんが、卒業論文執筆の一環として当協会代表理事の菊池にインタビューを行いました。
研究の背景と目的
東京都におけるアフォーダブル住宅の在り方と推進方法に関しての考察がテーマでした。
研究の背景は、2025年現在、東京都の住宅価格が高騰し、中間所得層が手に入りやすい住居が限られてきている。
また東京都では、アフォーダブル住宅の普及に向けて、ファンドを創設する計画が推進されている。
今後東京都に住む人にとって(手に入りやすい価格の)住宅と普及する方法を提案したい。
東京都の住宅課題
都内で中間所得層(年収300〜800万円ぐらい)の人々が、手に入れやすい価格で家を購入できるようにするためには、一般に「光熱費を含む住居費が総所得の30%以下である住宅」をアフォーダブル住宅の定義としています。
これは近年住宅価格の高騰が著しい海外の都心部で広まった考え方です。東京のような大都市圏で住居費が高騰する中で、人々が安定した暮らしを長期で続けていくためには「手に入れやすい価格の住宅」を意味するアフォーダブルな住宅の積極的な供給が望まれる。
しかし、その実現には以下のような課題があります:
・公平性の確保
・土地と建物の価格バランス
・所得と住宅価格の不均衡
・光熱費や税金などの追加費用など
地域ごとの価格差や実際の家計負担について、政府の積極的な関与と分析、法整備が求められます。
空き家再生の可能性
東京都内での住宅普及においても、空き家の活用が大きな鍵となります。特に、高齢者が所有する空き家の多くは、荷物が片付けられないことが原因で放置されています。この問題に対処するため、当協会では「おうち就活ノート」を活用し、所有者の意思を明確にして家族間での共通認識をつくるという取り組みを進めています。
また大田区や世田谷区など、空き家が増加している地域では、再建築不可能な物件の再生や活用に取り組むことで、住める状態にした空き家をアフォーダブル住宅として提供する可能性があります。当協会の理念である「空き家再生を通して日本中を笑顔に」を実現するため、空き家問題の解決と入手しやすい住宅の市場提供を両立する方法を模索しています。
まとめ
劉さんの研究は、東京都のアフォーダブル住宅に関する具体的な提案を目指しており、当協会の活動もその一助となる可能性があります。今後も私たちは理念に基づき、地域社会のニーズに応える形で空き家の活用に取り組んでまいります。
空き家再生協会